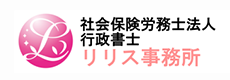最近、「自社で生活支援もやれば、コストが浮く」「支援機関に頼らなくても簡単にできる」と、軽く考えて生活支援を始める企業が増えています。
ですが、私は声を大にして言いたい。
生活支援は、派遣の延長線上にあるような“作業”ではない。
それは、人を育てる“営み”であり、育児や教育に近いものです。
特定技能で来日する若者たちは、日本の文化も、常識も、職場の空気も最初は理解していません。
何度言ってもルールが守れなかったり、注意されて「なんで自分だけが?」と不満を口にすることもあります。
中には、同じ国の他社の人たちが注意されていないのを見て、「不公平だ」と感じる子もいます。
企業様からも「この子、ちょっと質が悪いね」と冷たく言われることもあります。
でも、その言葉の裏にあるのは、「人を育てる」という視点の欠如です。
文化も教育も違う若者に、信頼関係も築かずにルールだけを押し付けても、伝わりません。
だからこそ、生活支援には時間がかかるし、夜や休日に及ぶことも多い。
ときには裏切られるような経験もあるけれど、それでも信じて寄り添う。
それが、本当の意味での「支援」だと思います。
支援料がもったいないから、うちでやる。
業務の一環でやる。
そう考えて始める支援は、やがて制度の信用を壊し、若者たちの未来を潰します。
生活支援とは、「仕事を与えること」ではなく、「生き方を育てること」です。
それはまるで、子どもを育てるように、手間も時間もかかること。
だからこそ、派遣業務の延長で気軽に始めるべきものではありません。
覚悟と責任を持って、初めて成り立つものです。
日本社会は今、少子高齢化と労働力不足のただ中にあります。
そんな中で、若い外国人の力を借りるのであれば、
同時に「人として育てる責任」からも逃げてはいけません。
生活支援は、“業務”ではなく“覚悟”です。